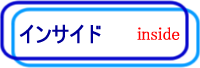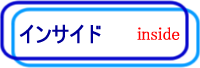※以下、所属学年は執筆当時のものです:
国際研究交流報告
留学報告
石橋 遼
(博士後期課程3年, 齊藤研究室)
経頭蓋磁気刺激法(Transcranial Magnetic Stimulation)と呼ばれる神経科学的な実験手法を修得するために、マンチェスター大学実験心理科学科の神経科学および失語症研究ユニット(Neuroscience and Aphasia Research Unit: NARU)に6週間滞在しました。人間の脳の一部に頭蓋骨の外から直接的な刺激を与え,それによってその脳部位のもつ機能を確かめようとする最新の実験手法です。滞在先のMatthew Lambon Ralph教授やGorana Pobric博士に細かにその技術を教えていただき,また実際にその手法を使って脳の意味認知機能を探索する研究に共に従事させていただきました。滞在先ではさらに認知神経科学専門の学生だけではなく、失語症のリハビリテーションの専門家、コンピュータモデルによる計算モデルの研究を行う研究者・院生も共に活動しており、それぞれの側面からお互いの研究について日常的にディスカッションをしながら、相乗的に研究成果を挙げていることに非常に感銘を受けました。英語でのディスカッションの早さについていけないと感じることも多々ありましたが、滞在中に関連する論文を多く読み,それに基づいて質問やディスカッションを行う中で、研究知識と英語能力の両方の面に置いて,大きく前進させてもらうことができたと感じております。その後Lambon Ralph教授が来日されたおりに自分の考えた研究のアイデアをお伝えし、興味を持っていただけたことで2008年10月?12月に再び訪問させていただき、共同の研究計画を進めさせていただいています。
私の研究留学においては特に「訊く」ことが重要だったと思います。最初は会話や話を普通に聞いているだけでは半分も分からない状況だったのですが、分からない点は後からでも訊ねるようにし、また会話でうまく訊ねる自身が無い時にはメールで質問をさせてもらうようにしていました。これによって自身の背景知識も増えましたが、私の周りの人々も私に取って何が分かりにくい点か理解してくれるようになったようでした。その結果として滞在後半には会話も比較的スムーズに行われることが増えたと感じています。
6週間の滞在を行ったことで新しい実験手法を体得でき、さらに他の研究者や博士課程大学院生との大変貴重な交流を持つことができました。研究者を目指す者として非常に大きい体験をさせていただけたと思っています。
留学体験記
上野 泰治
(留学のため休学中, 齊藤研究室)
当講座の魅力として、海外の研究機関において勉強する機会が多いことが挙げられます。ひとつには、先生方や先輩方が海外の研究者達と共同で研究を進めておられ、そういったリンクを通じて海外の研究機関に目を向けることが出来ます。また、当講座の子安教授が中心となって進めているグローバルCOEプログラムにおいては、院生が海外の研究機関で学ぶことを積極的に進めており、それを充分にサポートする費用が配分されています。
私の最初の留学体験も、グローバルCOEプログラムの前進である21世紀COEプログラムに割り当てられたGrantに支えられてのものでした。英国York大学で、Alan Baddeley教授とGraham Hitch教授、そしてRichard Allen博士のご指導のもとに、「作動記憶における情報の統合メカニズム」について研鑽を深め、更に、実験計画の立案・実施・discussionという過程を共にすることができました。
まず、彼らと接して勉強になったことは、データの再現性を大事にするということでした。彼らの論文の内容を発展させようと思って考案した私の研究計画に対し、彼らの出した結論は "Taiji, keep it simple. At first, let’s replicate the data from our paper.”というものでした。つまり、新しい計画の前にまずは追試してみようか、ということです。信頼できる結果でなければ、それらを発展させても仕方のないこと、という意味かと思います。
別の例も挙げられます。日本で得られた興味深いデータについて報告した際にも、「ではこっちに来て、それの追試実験を行ってくれ。」というのが彼らの最初に出したコメントでした。結果としてYorkでは追試が出来ず、追試に失敗した理由がわからない限り、そのデータでは論文を書かないということになりました。明らかに落ち込んだ顔をした私に対し、Alanの “It’s absolutely better than publishing unreliable data.” という力強いメッセージは、今でもありありと記憶に残っています。”Absolutely.” と横で叫んだGrahamの高い声も忘れられません。 Manchester大学のMatthew Lambon Ralph教授と行った一連の研究についても、そこには追試ということが非常に大きな重点を占めていました。
自分の結果に対し、「斬新だ。しかし追試されるのか?」という視点を持つことは、自分自身の学術界における信用を高めてくれると信じています。蓋を開けてみると、10近くの実験の中で、追試実験は実に半数近くを占めていました。追試を行ってみる、ということは非常にハードで、間違いなくストレスフルなものではありますが、研究者を目指す者として、そこから得られる質は何事にも代え難いものであると信じています。
また、英国の先生方、院生の皆様は、研究と日常生活のバランスを非常に大事にします。土日は必ず家族・大切な人達・友人との触れ合いに充て、研究など絶対にしません。月曜日には必ず、”How was your weekend?” と聞かれます。平日も、17時前になれば帰宅し、自分の余暇を大切にします。きっとそれは彼らの脳をリフレッシュし、アイデアが凝り固まらないようにしているのでしょう。これを真似ることは二の足を踏みたくなるのが本音ですが、きっとこれこそが彼らのproductivityの元になっているのだと思います。
最後に、絶対に日本語に逃げられない状況で、英語で共同研究を行うことは非常に辛いことであります。しかし、日本語に逃げることなくもがいた経験は、自分の英語力となって報われます。それは、間違いなく自分の研究にプラスとなっていると感じています。
留学報告
木村 洋太
(博士後期課程3年, 吉川研究室)
M1の後半(1月?3月),及びM2の夏(9月)の約4ヶ月間, visiting researcherとしてアメリカのCalifornia工科大学に研究留学させていただきました。現地では,lab meeting(自分の発表2度を含む)に参加し,研究打ち合わせ,予備実験,本実験を実施してきました。大学には実験参加者募集を効率的に行えるようなオートシステムが完備されており,実験者は講習をうけることによって自由にシステムを利用できるようになっていました。
また,世界中の意欲ある学生をtemporally assistantとして採用し,一流の研究に参加させながら指導するプログラムが義務化されていました。私の所属した研究室では,事前にプロジェクトを立ち上げて議論し,学部生はPD及び大学院生の下で直属の指導をうけ,かつそのPDと学生を指導教授がさらに管理するという体制をとっていました。私は,効率的な成果の達成だけでなく,研究指導力も求められていると感じました。
私自身の研究では,実験準備ができると教授自らが被験者として実験を体験し,その日から次々に参考文献を紹介して下さいました。学生と指導教官の距離が非常に近く,大学にくる度に実験室をのぞいては,実験の経過などを伺ってくれました。数分でも毎日のように研究や生活などの話をするので,ほどよい緊張感と意欲が保たれたと思います。
一番の印象は,研究のかなり早い段階で投稿するjournalを意識するよう求められたことです。知りたいことは何かというより,知りたいことがわかった時にどのjournalに載るのかを考えさせられました。それは当然,「ある論文がなぜそのjournalに掲載されたのか」を考えながら論文を読むことにつながりました。知識を取り入れ,研究を正しく批評し,面白いものは何かを漠然と考えようとしていた私には,意識の変わった瞬間でした。
研究が面白くなる瞬間は様々なものがありますが,私はこの留学が一つの転機になったと強く思っています。
留学報告
小宮あすか
(博士後期課程2年, 楠見研究室)
私は「文化・社会が人の心にどのような影響を与え、人がどのように新たな文化を作り出していくのか」ということに興味があり、そのために文化比較という手法を使用することがあります。文化比較研究とは、すごく大雑把に言えば、異なる文化で同じ状況を作ったときに、同じ状況でも文化によって人々が異なる反応をする、その特徴をとりだそうとするものです。こうした興味から、ウィスコンシン大学の宮本百合先生と日米での後悔の比較研究を行っており、その研究の打ち合わせのため、今回3ヶ月間滞在させていただきました。宮本先生は、私が修士1年生の頃に楠見研究室にPDとして滞在していらっしゃった方です。留学体験記とは異なりますが、こうした優秀な先輩方とお知り合いになれるのも、この講座の魅力だと思っています。
 マディソンは2つの大きな湖に囲まれた都市であり、ウィスコンシン州の州都です。大学はちょうど湖に挟まれた細長い陸地にあり、生協には湖に面したテラスがあります。夏の期間は、ここで毎日ブルースやバンドのライブが繰り広げられており、私もときどき出かけて音楽を楽しんでいました。また、州議事堂の前では毎週土曜日の朝市が開かれており、たくさんの人々でにぎわっています。余談ですが、「マディソン郡の橋」の舞台のマディソンとは異なる都市です(映画の舞台はアイオワ州にあります)。 マディソンは2つの大きな湖に囲まれた都市であり、ウィスコンシン州の州都です。大学はちょうど湖に挟まれた細長い陸地にあり、生協には湖に面したテラスがあります。夏の期間は、ここで毎日ブルースやバンドのライブが繰り広げられており、私もときどき出かけて音楽を楽しんでいました。また、州議事堂の前では毎週土曜日の朝市が開かれており、たくさんの人々でにぎわっています。余談ですが、「マディソン郡の橋」の舞台のマディソンとは異なる都市です(映画の舞台はアイオワ州にあります)。
 「打ち合わせなんてメールでやりとりすればすむじゃないか」と思われるかもしれませんが、実際にパソコンを並べて研究の打ち合わせをするのと、メールでやりとりしているのとでは、同じ“打ち合わせ”といってもはかどり具合が全く異なります。その場で意見を交換し、一緒に考えると、自分だけで考えているときよりもよいアイデアが浮かんだりするものです。また、実際にアメリカで(必死に)生活し、生の文化に触れることができたのも貴重な体験でした。今回の滞在ではウィスコンシン大学で社会心理学を学ぶ院生さんたちのランチをかねた勉強会に参加することができたのですが、非常に活発な議論が交わされており、ついていけずによく悔しい思いもしました。その一方で、勉強会中に、日本ではありえないほど大きなハンバーガーをほおばりながら、でも「研究発表会の発表どうしよう?」とか「博士論文の面接どうだった?」と、日本の学生と同じような話をしている姿を見て、文化や言語が違っても生活は似たようなものなのだなぁ、と、なんだか不思議な気分でした。 「打ち合わせなんてメールでやりとりすればすむじゃないか」と思われるかもしれませんが、実際にパソコンを並べて研究の打ち合わせをするのと、メールでやりとりしているのとでは、同じ“打ち合わせ”といってもはかどり具合が全く異なります。その場で意見を交換し、一緒に考えると、自分だけで考えているときよりもよいアイデアが浮かんだりするものです。また、実際にアメリカで(必死に)生活し、生の文化に触れることができたのも貴重な体験でした。今回の滞在ではウィスコンシン大学で社会心理学を学ぶ院生さんたちのランチをかねた勉強会に参加することができたのですが、非常に活発な議論が交わされており、ついていけずによく悔しい思いもしました。その一方で、勉強会中に、日本ではありえないほど大きなハンバーガーをほおばりながら、でも「研究発表会の発表どうしよう?」とか「博士論文の面接どうだった?」と、日本の学生と同じような話をしている姿を見て、文化や言語が違っても生活は似たようなものなのだなぁ、と、なんだか不思議な気分でした。
滞在中、言語が通じないこともさることながら、実は食事もかなり困ったことのひとつでした。3ヶ月の滞在だったので料理の材料・器具をそろえられず、お米やしょうゆ味・味噌味がなかったのが、かなり辛かったです。また、日本では気軽に院生同士で夕食を食べにいって「軽くビール一杯」を飲んだりするのが日常茶飯事なのですが、アメリカではそうもいかず、日本にいる後輩から「この間皆で呑みにいきました!」というメールが入っていたときには妙に羨ましかったりしました。
アメリカに滞在したのは第一には研究のためだったのですが、アメリカの文化を実際に体験し、振り返って日本の文化や自分のおかれた環境を再考する機会を得たという意味でも、非常に有意義なものだったと思います。
知の宝庫の扉を開けてみて
志波 泰子
(博士後期課程3年, 子安研究室)
私の学生時代は大学紛争によるロックアウトが1年近く続き、大学再開後は、父の重患という家庭の事情も重なって、十分な勉強もせずに経済学部を卒業してしまいました。いつかは大学でもう一度、勉強したいと思っていたのですが、家計のやりくりと子育てに明け暮れて、大学で学び直すという気持ちはどこか遠くへ行ってしまっていました。
10年ほど前思いがけず京都に住みつき、最初は百万遍に並ぶ古本屋が珍しくて、古本漁りに明け暮れていました。そのうち知の宝庫を横目に見て本屋に通うだけではつまらなくなり、もう1度大学生になって「人間の心」について勉強しようと思いました。すでに子どもたちはそれぞれの大学へ進んで親元を離れていましたが、あれやこれやと心をくだいて育て、親子としては良好な関係を保ってきたはずなのに、自分の子どもの心すらほとんど分かってはいなかったという思いがあったからです。
初めは教育学部の聴講生になりました。講義では、人間性の本質が生まれによるものか育て方によるものかという「遺伝と環境」をめぐる古くて新しい論争が今も続いていること、現在では母親の育て方だけに責任があるわけではないという説が有力であると知り、いくらかほっとしました。発達という視点から人間の心を理論的に知りたいと、社会人に開かれている専修コース修士課程へ入りました。心についての何かが分かったと思うには2年間では短かすぎ、現在は教育認知心理学博士後期課程に在学しています。
数学的基礎知識が0に近い私に、心理統計法を用いる心理学は困難な分野であり、若く優秀な院生の皆さんが丁寧に教えてくださるのですが、勉強しても頭は良くならないという某説のとおり、加えて老化のためもあって、やっと理解できた統計学の知識は覚えた先から忘れるといったことの繰り返しです。現実は老いたる駄馬に似た脳内環境なのですが、恥しさは脱抑制しての研究生活です。
私の研究分野は幼稚園や保育園のお子さんたちの協力なしでは成り立ちません。これまで沢山のお子さんたちに実験研究に参加していただきました。本当に有難いことと感謝しております。大学院で学んだことは小さな子どもたちの発達環境の充実へ向けて何らかの形で、お返しをしたいと思っています。
国際学会発表報告
田村 綾菜
(博士後期課程3年, 子安研究室)
私はM2の7月に,the 19th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development(ISSBD)に参加しました。このときが初めての学会発表で,しかも国際学会ということでかなり不安でしたが,経験豊富な先輩とご一緒させていただくことができ,とても充実した国際学会デビューとなりました。また,D2の7月には,the 20th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural DevelopmentとXXIX International Congress of Psychologyという2つの学会に参加しました。たまたま近い時期に,同じドイツで開催されるということで,はりきって2つも申し込んでしまいましたが,2回分のポスター発表の準備は思った以上に大変でした。今後,国際学会に申し込む際には,準備のためのスケジュールについてもよく考えようと思いました。
国際学会に参加する醍醐味は,なんといっても,普段自分が読んで関心を持った論文の著者である研究者と,直接話ができるチャンスがあるということだと思います。私自身,お会いしたい先生に事前にメールをして,学会で会う約束をし,実際にお会いしてお話しすることができたことが何よりの収穫でした。また,国際学会では,国内の学会に比べてキャンセルになる発表が多く,どうしても聞きたい発表は,可能であれば事前にメールなどでアポイントをとっておくとよいと思いました。
また,これまで国際学会に参加して痛感したことは,日頃からの英語の練習が必要だということです。私は,ドイツで2つの学会に参加する1ヶ月前から,同じ学会に参加する先輩,後輩と一緒に,週に1回集まって発表練習をしました。英語でのプレゼンや質疑応答の練習になったことはもちろん,ポスターのレイアウトに関してや研究の内容そのものにもつっこんで議論することができ,非常に有意義なものとなりました。それでもやはり,海外の研究者と英語で議論するのには非常に苦労しました。直前だけでなく,普段から英語で議論を行う機会をつくる必要があると感じました。
国際学会で発表することはいろいろ大変なことも多いですが,私にとっては海外へ行くこと自体が貴重な機会であり,研究のモチベーションを高めてくれるもののひとつとなっています。
一院生の声
常深 浩平
(博士後期課程3年, 楠見研究室)
いささか仰々しいですが,「求めよ,さらば与えられん」という言葉が本講座の特徴を端的に示しているのではないでしょうか。本講座では,学生の求めに応じて様々な機会が与えられます。その中から,自分にとってためになっている幾つかを記したいと思います。
たとえば,「教える」機会。まずは授業の補佐や半期に2度ほどの院生グループでの学部生への演習実施,その後,学部生・院生を班員とする通年の演習の班長というように,順を追って,「教える」という機会を得ることができます。また,「教わる」機会にも恵まれています。普段の授業やゼミの質が高いのはもちろんのこと,集中講義に来て頂く先生は学生の希望が最大限に活かされて決まります。加えて,論文の投稿や日本学術振興会の特別研究員への応募などに関して「機会」を得てきた先輩方から貴重な情報を「教わる」ことも多いですし,またそうした自分の経験を活かして後輩に「教える」ことができるという良い循環が生まれています。それぞれが貴重な経験です。
他にも,「外へ行く」機会,つまり海外を含めた国際学会発表への支援体制が充実していることもその一つでしょう。認知心理学の研究は国際的に進んでいるため,自分の研究を広く発信するという点でも,また最新の研究に触れるという点でも,国際学会に参加することは大きな成果につながります。この点についても経験豊富な先生方や先輩達のサポートがありますし,また学生にとっては大きな壁になることも多い資金面でも,グローバルCOEの海外派遣費用など多くの援助が受けられる環境が維持され続けています。僕自身について言えば,COEの海外派遣費用や日本学術振興会の特別研究員の科学研究費によって,最初は先輩と一緒に,後々には一人ででも,年に一度のペースで海外発表に赴いています。毎回様々な出会いや発見がありますが,近年で一番の収穫は,アメリカのMemphis大学で行われた2008年のAnnual Meeting of Society for Text & Discourseで,自分の研究分野の大家である. Colorado大学のWalter Kintsch教授と直接知り合う機会があったことです。自分の発表に意見を頂いたり,また彼の立てたモデルの細かい点について直接質問ができたりと非常に有意義な時間を過ごすことができました。具体的な研究上の利点を抜きにしても,このような貴重な経験は研究を続けていく上で大きなプラスになっていると感じます。
どの機会にせよ,押しつけられることなく,自分で得たいと思った時にその機会が得られるというのは本講座の特徴であり,かけがえのない利点だと思います。
留学報告
中嶋 智史
(博士後期課程3年, 吉川研究室)
修士1年,および2年の春休み(修士論文の提出後)にUniversity of StirlingのDepartment of Psychologyに滞在し,Dr. Steve Langtonと共同研究を行った.もし,この機会がなかったら私の修論は全然違うものになっていただろう.何故なら,Stirlingで行った実験がその後の私の修論の基礎になったからである.
Steveはとても気さくな人で,私の大変つたない英語に対していつもしっかりと耳を傾けてじっくりと聞いてくれた.また何度も何度もミーティングを行い,相互の意思の疎通を図ってくれた.おかげで,実験計画から論文執筆,さらには雑誌への投稿まで持っていくことができた.私にとって大変大きな出会いであったと思う.また,Stirlingの滞在中には,英語で口頭発表する機会にも恵まれた.英語での口頭発表は初めての機会であったし,顔研究の第一人者であるDr. Bruceに発表を聞いて頂けて万感の思いであった.
生活面においても大変貴重な体験をすることができた.大学内にある短期滞在者用の共同宿泊施設に宿泊したのだが,そこで海外から来ていた研究者の人達と知り合うことができ,共同のキッチンで一緒にディナーを作って食べたり,登山をしたりととても楽しく過ごすことができた.もちろん,海外に滞在することは楽しいことばかりでなく,周囲の話していることが全く理解できなかったり,自分の伝えたいことが正確に伝わらなかったりして,とても悔しい思いをしたこともあるし,孤独感に襲われる場面もあった.
海外でやっていくコツはやはり積極的になることだと思う.そして,一緒に頑張れる仲間を作ることだと思う.海外では,日本にいる時と違って何も言わなくても分かってくれる人はほとんどいない.研究会や飲み会で黙っていても誰も気を遣ってはくれない.だから,何でもいいから,とにかく自分から話を振ったり,質問をしたり,飲みに誘ったりすることが一番の近道だ.僕の場合は一緒に共同宿泊施設に泊まっていた人を飲みに誘ったところから突破口が開けた.海外から来ている人達と話す中で,自分だけじゃなくて,他の国から来ている人達も同じように孤独を感じていたり,英語ができないと思っていたりすることも分かったし,共感し合えた.また色々な人と仲良くなれたことで,心理的な余裕ができた.
海外に行くことは大変な労力だし,思うようにいかないことだらけだけど,それに見合うだけの価値はあると思う.是非,機会を逃さず海外に行ってみて下さい.
留学報告
古見 文一
(修士課程2年,子安研究室)
修士1年次の春休みにUniversity of Birmingham のDepartment of Psychologyに留学させていただきました。University of Birmingham では自分の研究で引用した論文,書籍の著者であるDr Ian Apperly と自分の研究について,また近年,非常に多義的になってきているtheory of mind の概念や,Apperly 先生自身が提唱するmindreading の概念について深く議論することができました。また,週に1回お昼に開かれるティーパーティにも参加させていただきました。そこでは立ったまま紅茶を飲みながらアカデミックな会話が自然と起こるとても素敵な空間でした。
滞在中は他に,Lancaster University と University of Stirling にも訪問し,授業に出席したり、現地の研究者と議論を行ったりしました。Lancaster University では Prof Charlie Lewisに2日間つきっきりで行動させていただいて,学部生向けの授業,院生向けのセミナーなどに連れて行っていただきました。また,先生がされている歌のアクティビティにも参加させていただきました。また,自分の研究についてもいろいろコメントをしていただき,Lewis 先生が今行っている研究についてもお話していただき,また発達研究の設備を見せていただきました。University of Stirling では Dr James Anderson と Dr Martin Doherty にお世話になりました。こちらではScotland の郊外にある Burnという1791年に建てられた施設での合宿に現地の学部生,院生,教員の先生方と一緒に行かせていただきました。みんなで一緒に寝泊まりし,大自然の中を散策しながら学問的な話をするという貴重な体験をすることができました。
留学生活を通して,英語には本当に苦労しました。相手の言っていることはわかるのにこちらからはなかなかスムーズに話ができないということや,クラスのみんなが一斉に笑った時も自分だけわからないということもありました。何より,自分の研究についてうまく説明ができない,自分の研究にしていただいたコメントの英語がところどころわからないということがとても悔しかったです。英語をもっと訓練して,次に留学するときにはもとうまくコミュニケーションをとりたいと思いました。
短い期間ではありましたが,出発前から先生方に多くのサポートをしていただいたおかげで,とても充実した実りのある留学生活を送ることができました。University of Birmingham では喜多壮太郎先生と短い時間でしたが面会をすることができ,海外での日本人研究者についてのお話を聞くことで,自分の研究を海外に発信するということへの意識を持つことができ,また,イギリス滞在中に出会った研究者のほとんどから「英語で論文は書かないの?絶対書くべきだよ」と声をかけていただいたことで,英語論文執筆への意欲がとてもわきました。修士1年目というスタートの時期に多くの貴重な体験をすることができたことを現地でお世話になった方々,何から何まで自分の留学を支えてくださった先生方に深く感謝しています。
(2011年4月8日記)
留学報告
溝川 藍
(博士後期課程2年, 子安研究室)
修士1年次の春休みにThe University of Auckland のStudent Learning Centre (SLC) へVisiting Researcherとして留学させていただきました。SLCは,学生のアカデミックスキルを向上させることを目的の1つとした機関で,私の滞在期間中にもスキルアップのためのワークショップが多く開かれていました。各学生が自分の課題に見合ったコースに参加できるようになっており,私は,ディスカッション能力・ライティング能力を高めることを目的とした1週間のワークショップに参加させていただくことになりました。
私の現地での主な活動は,①心理学部で行われる心理学フォーラムでの口頭発表,②論文の執筆でした。留学第1週目に上記のワークショップに参加させていただいたことで,留学の目的である口頭発表や論文執筆に対する基礎体力をつけることができました。
①口頭発表
発表準備はSLCで進め,受け入れ教員であるDr. Emmanuel ManaloがSLC内で発表練習の時間を設けてくださいました。そこで先生やスタッフの方から,適切な英語表現,発音,効果的な話し方(話す速度や身振りなど)をご指導いただきました。初めての英語による口頭発表に当初は大きな不安を抱えていましたが,練習時間以外にも,スタッフルームで先生方から様々なアドバイスをいただく等丁寧に対応していただき,十分な準備をすることができたと思います。フォーラムでは,日本の子どもの感情理解の発達について発表をしました。フロアからは質問やご意見を多数いただくことができ,興味深く聞いていただけたと感じました。また,発表後には,私の研究に興味を持ってくださった方とディスカッションをする機会を何度か持ち,日本と欧米の文化差についての貴重なご意見をいただき自分自身の研究への問題意識が深まりました。
②論文執筆
滞在中に論文を執筆し,SLCのスタッフの方に数回にわたって丁寧な英文チェックをしていただきました。修正作業を通じて多くの適切な英語表現を学ぶことができました。私が書いた英文を修正していただく際に,その文章で伝えたいことを別のニュアンスで捉えられてしまい,修正後に内容が異なってきてしまうことが何度もありました。その度に,自分が言わんとしていたことを修正者の方に正確に伝え,改めて英文を考え直す必要がありました。このことも自分の意見を英語で伝える良い訓練になったと思います。
1ヶ月という短い期間ではありましたが,多くの方に支えられて実り多い留学生活を送ることができました。また帰国後も,現地での研究者の方々との出会いが新たな出会いを呼んでおり,現在の研究生活をより充実したものにしてくれています。大学院のスタートの時期にこのような貴重な時間を持てたことを嬉しく思い,お世話になった方々に心から感謝しています。

|